
能島城とは何か
能島城は、瀬戸内海の激しい潮流に守られた「海賊の城」です。今回は、偶然乗船できた潮流クルーズ体験を軸に、航空写真と現地観察から“海城の防御”を整理します。
駐車場 アクセス
現在では、令和2年(2020)6月2日より上陸が再開され、「能島城跡上陸&潮流クルーズ」が実施されております。
たまたま偶然、訪問したのが令和2年(2020)6月2日の日でした。漁港に寄ると、クルーズ出向と重なり今回の乗船という流れです。
航空写真
こうみてみますと、島と島の海峡の良い場所にお城があります。北側には何やらビーチも確認できます。
能島城は「島にある城」ではなく、海峡の流れ(潮流)を防御として組み込んだ配置に見えます。航空写真で俯瞰すると、その意図がとても分かりやすいです。
現地レポート
「海城をゆく」企画第一弾!

県道49号線沿いに車を停めて、能島城の方を見てみます。島全体が城って今まで見てきた山城とは全く違う趣向で興味津々。「海賊の城」かあ~。

鯛崎島を見てみる。うーーん、平坦地が見える。この上に建物があったんだろうなあ。

能島城の方も上部には平坦地。一体どんな建物があったのだろうか。それにしても流れがめちゃめちゃ早い。これだと、小早船でどうやって近寄っていたのか気になります。普通に転覆とか多発ではないだろうか。
まさに、潮流に守られた「島城」、砂嵐に守られた「バベルの塔」、龍の巣に覆われた「ラピュタ」ではないか。
う~~ん、接岸方法が気になりますね

お!何やら高速船を発見
潮流体験

近くの「今治市村上海賊ミュージアム」を訪問後、たまたま漁港でお昼でも食べようと漁港に寄ってみる。すると、おばちゃんから「出るので、いかがですか」とお誘いを受ける。これは、さっき見かけた高速船。
そして、「ま、時間もあるし良いか」と何も考えずに乗船しました。しかし、それが、

めちゃ、面白かった。
サプライズとはまさに、このこと

いざ出発!

管理人的には、船でないと近づけないし、道からじゃ遠いので、のんびりクルーズでもしながら、優雅に船の上から写真撮影と思っていましたが!このクルーズタイトルは

潮流体験!
なのであります。

白波が立っているぐらい流れが強い。

鯛崎島を横目に見ながら

鯛崎島と能島の間を突き進み、


ぐるりと周遊。そして、能島に寄る寄る。ちょっと寄り過ぎです。岩石がすぐそこに見えてます。しかも、潮流体験ですので、エンジンを止め?て、潮流に乗って流されるという離れ業。
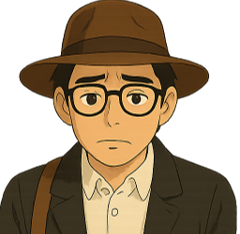
ぶつかる。ぶつかる!
こんな感じです↓↓↓
(実際の映像 後日の上陸編の際、この状況の撮影に成功しました。)
ちょっと!船長の腕、凄すぎませんか!

能島をぐるりと回り、北側へ。すると潮流が急に緩やかになる。しかも、上陸するのにちょうど良い砂浜が。なんという良港。ということは、この能島に接岸する方法はと考えてみると、主に3パターン。

①激流と激流の境を読み取り、北側から侵入するパターン
②凪の時間帯を見つけ出し、普通に接岸するパターン
③大型船での強引なパワー
のどれかかなあと思います。


本来だと、ここから接岸して上陸見学を行っているようです。しかし、今回は、残念ながら上陸見学はありませんでしたが、普段の山城登りでは体験できない「海賊激流体験」ができました。

リアルライド系アクティビティ
でした。団体で行けば、大盛り上がり間違いなしです。
「今治市村上海賊ミュージアム」


「村上海賊」とは、いったいどのような集団で組織なのか、ここでしっかり学ぶことが出来ます。特に、管理人としては、船について学べた点が良かった。
安宅船(あたけぶね)
戦国時代〜江戸時代に使われた大型の軍船です。主に兵士や武器を大量に運ぶための輸送船として用いられました。
甲板が広く、弓や鉄砲を使う兵士を多数乗せることができるため、海上戦での主力となりました。江戸時代の海上防衛や海賊対策にも使われています。
関船(せきふね)
中型の軍船で、安宅船よりは小さめですが機動力があります。短距離の輸送や海上での機動戦闘に適していました。関船は速さと取り回しの良さが特徴で、偵察や奇襲にも使われました。
複数の櫂(かい)を使って漕ぐため、風が無い時でも動ける船です。
小早船(こばやぶね)
小型の速い船で、主に偵察や伝令、急使の移動に使われました。軽快な動きが特徴で、敵の動きを探ったり、素早く情報を伝える役割を担いました。戦場だけでなく、漁業や運搬にも使われることがありました。
しかし、最強の船は
戦国時代の海戦において、最強の戦力と言えばやはり、安宅船に鉄板を張った「鉄甲船」でしょう。
通常の木造船が多かった当時、鉄を装甲に用いるという発想は非常に画期的であり、その防御力の高さは敵の攻撃を大きく減らすだけでなく、戦闘における優位性を決定づけました。
こうした革新的な船を建造したのが、天下統一を目指した織田信長や豊臣秀吉というのは、やはり戦略面でも技術面でも一歩先を行っていた証拠です。
鉄甲船の登場によって、海戦の様相は大きく変わり、それまでの木造船による打撃戦や白兵戦とは異なる、新たな戦いの形が生まれました。
敵の砲撃をものともせずに突進できる鉄甲船は、戦場における恐怖の象徴となり、多くの戦局で勝敗を分ける決定的な存在となったのです。
まさに、織田信長と豊臣秀吉の時代は、戦国時代の中でも技術革新と戦術革新が融合した「一歩先を行く」時代だったと言えるでしょう。
ここでは、「小早船」の復元も見ることができます。
まとめ
能島城は、石垣や堀ではなく、潮流そのものを“城壁”として使う海城でした。山城とは違う防御の形が、体験としてそのまま分かるのが面白い点です。
潮の速さ・接近の難しさ・凪の帯の存在まで含めて、能島城は「自然と一体の要害」だと感じました。

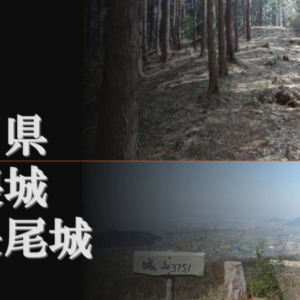

コメント