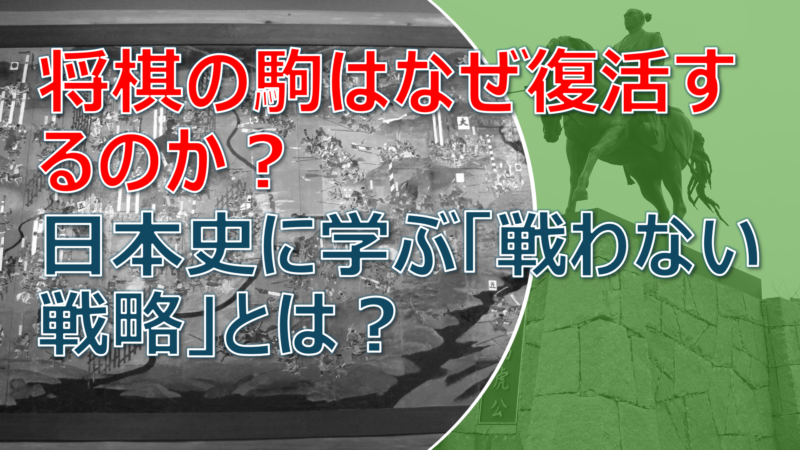
はじめに|なぜ「強者」が必ず勝つとは限らないのか
日本史を眺めていると、単純な力比べでは説明できない勝敗が数多く存在します。
兵の数で劣っていても勝つ。
武勇で勝っていても崩れる。
その差を生んでいるのは、戦場での腕前ではありません。
戦いが始まる前に引かれた一本の線です。
なぜ弱者が強者に勝てたのか。その答えは、気合でも奇策でもありません。
勝とうとする以前に、勝負が成立しない条件を作っていた。
今回は、この日本史に繰り返し現れる思考を「和製戦略」として整理します。
扱うのは理論ではなく、設計され、実装され、現場に刻まれた戦略です。
藤堂高虎|城郭は「戦意を折る装置」
築城名人として知られる藤堂高虎の城を前にすると「堅い」というより、まず圧倒される感覚が先に来ます。
広い水堀。すぐ近くに見えているのに、なぜか一向に近づけない天守。見上げるしかない高石垣と、その背後に積み上がった膨大な土木量。
ここで高虎が狙っているのは、戦闘の巧拙ではありません。攻め手に「勝てるかどうか」を考えさせる前に、「これは無理だ」と感じさせること。つまり、戦う前に戦意を削り取る設計です。
攻め手に「勝ち筋」を想像させない構造
高虎の城では、まず外周で足が止まります。広い水堀は渡れそうで渡れず、天守は近くに見えるのに距離感が狂う。攻め手は「どこから詰めるのか」「どう突破するのか」という基本的な勝ち筋を描きにくい。ここで既に、心理的な主導権は守り手に移っています。
ようやく城内に入ったとしても、待っているのは一本道ではありません。
虎口は何重にも重なり、門が門を塞ぎ、折れと屈曲で勢いを殺される。突破したと思った瞬間、横から矢が掛かる。前に進めば詰まり、引こうとすれば背後が塞がる。勇敢さが試される場面ではなく、消耗と滞留が積み重なる場です。
数を揃えた側が最も嫌がるのは、「押し込めば勝てる」という感覚を失うことです。高虎の城は、攻め手にその感覚を徹底的に与えません。兵が多くても前に出せず、突破しても次が見えない。こうして攻め手は、戦いながらではなく、進む前から心が削られていく。
一方で、虎口を越えた場内(曲輪の中)は、意外なほど広く、がらんとしていることが多い。これは守りが薄いのではなく、守り手が自由に動ける余白です。
入口で攻め手を詰まらせ、内側では守り手が再配置できる。この対比が、高虎の城を単なる要塞ではなく、「攻めたくなくなる城」にしています。ここで勝敗は、最後の決戦ではなく、入口から天守へ至る途中で静かに確定していきます。
城は戦術ではなく、戦意を折る戦略
藤堂高虎の城は、「戦って勝つ」ためのものではありません。そもそも敵に「勝負を挑む気」を起こさせない。圧倒的な石垣と土木量、何重にも重なる門と虎口、そして近づけそうで近づけない配置。そのすべてが、戦う前に負けを悟らせるための装置として組み上げられています。
高虎の築城を見ていて感じるのは、強さそのものより、「これは長期戦になる」「これは割に合わない」という空気です。
相手の数や武勇を真正面から受け止めない。城郭とは、戦闘の技術ではなく、勝敗条件と心理を固定する構造物である。その考え方を、最も徹底して形にしたのが藤堂高虎でした。勝敗は、攻め手が勝ち筋を描けない途中で、すでに崩れ始めます。
設楽原の戦い|武勇を無効化した戦場設計

戦国史の転換点とされる設楽原の戦い(長篠の戦い)は、鉄砲の威力だけで語られることが多い戦いです。
しかし本質は、武器ではなく戦場そのものの設計にありました。武田軍の強さを、真正面から打ち負かしたというより、強さが出る条件を先に壊した戦いだった、と見る方が理解しやすいと思います。
強い軍は、強い形で戦わせなければ強さを発揮できません。設楽原では、その「強い形」を作らせない要素が重なっていました。
ここでも勝敗は、戦闘開始前から方向づけられていた可能性があります。つまり、勝敗は戦いの最後ではなく、突入が成立しない途中で固定されていた、と考えると腑に落ちます。
個の強さを出させない構造
武田軍の騎馬武者は、当時屈指の精鋭でした。しかし設楽原では、柵と地形によって突進力が分断され、一斉突入という最大の強みが発揮できませんでした。強さそのものを否定したのではなく、強さが現れない場を用意したのです。
一斉に押し寄せて初めて機能する戦法は、分断されると急速に弱体化します。
突進の勢いが削がれ、統制が乱れ、局地的に「少数が少数で戦う」形になる。ここでも数は、単に多い少ないではなく、「一度に出せるかどうか」が支配しています。
同時投入できる数を制限する
設楽原では、敵が一度に投入できる兵数が厳しく制限されました。その上で時間差をつけた攻撃が重ねられ、局地的優位が連続して生まれます。これは戦術の巧拙ではなく、数の同期を崩す戦略でした。
数が揃えば揃うほど強くなるはずの軍を、数が揃わない状態に固定する。その上で、攻撃側は同じリズムで力を出し続ける。結果として、局地の優位が連続し、全体の崩れへ繋がっていく。
設楽原は「強い者同士の戦い」ではなく、「強い形を奪った上での戦い」として見ると理解が深まります。勝敗は、最初の衝突から終局へ至るまでの途中で、連続的に決まっていきます。
戦場そのものを戦略化する
設楽原の勝敗は、戦闘が始まる前から大きく決していたと言えます。戦場が、武勇を発揮する舞台ではなく、武勇を無効化する装置として機能していたからです。
戦い方の工夫ではなく、戦わせ方の設計。
ここに設楽原の意味があります。戦場を「強さの比較の場」にしないことで、勝敗は別の次元で決まっていきます。これは築城と同じく、場そのものが戦略を背負っている例です。
強さは、最後の結果で否定されるのではなく、発揮できない途中で封じられます。
陶山訥庵|生態系を相手にした「戦わない政策」

江戸時代、対馬で行われた猪鹿追詰は、郡奉行であった「陶山訥庵(すやまとつあん)」による政策です。
これは害獣駆除というより、増殖構造そのものを断つ設計でした。
一匹を倒さない、仕組みを断つ
猪を一匹ずつ狩っても、被害は終わらない。訥庵はそう判断しました。
島全体を一つの単位として細かく区画化し、一つずつ潰していく。対象は人ではありませんが、
「数と流れをどう断つか」という発想は、高虎や設楽原と同型です。
目の前の一匹を倒すのではなく、増え続ける途中を止める。すると「被害を受け続ける」という勝負条件が消え、争いそのものが成立しなくなる。この発想は、戦場ではなく政策として実装されました。
三者に共通する和製戦略の核心|「戦わせない条件」を先に作る
三つの事例を並べて見えてくる共通点は明確です。誰も、目の前の相手を力で倒そうとしていません。
設楽原は、武勇を競っていない。
高虎の城は、攻める想像を抱かせない。
訥庵の政策は、戦いという枠組みを持ち込まない。
共通しているのは、
「どう勝つか」ではなく
「どうすれば勝負が成立しないか」
を、最初に設計している点です。
共通項①|「敵を倒す」のではなく「勝負を成立させない」
勝利条件を競うのではなく、勝負条件そのものを消す。ここに、日本的戦略の第一の特徴があります。
共通項②|「戦いの場」を先に支配している
三者が相手にしているのは、敵そのものではありません。戦いが起きる場です。地形、城郭、制度。いずれも、衝突が起きる前に勝敗を固定します。
共通項③|「力」ではなく「流れ」を見ている
三者はいずれも、
・個々の強さ
・瞬間的な勝利
・努力や勇敢さ
を主軸にしていません。
見ているのは、
・数がどう集まり
・どこで詰まり
・どこで止まるか
という流れです。
日本的戦略に通底する「途中の哲学」
ここで、日本的戦略に通底する思考が見えてきます。それが、「途中を重視する哲学」です。
設楽原は、結果だけ見れば一瞬です。しかし、その前段には無数の途中があります。高虎の城が機能するのも、天守に至る結果ではなく、至れない途中です。訥庵の政策も、成果ではなく、途中の積み重ねが流れを断ちました。
途中が正しければ、結果は自然に決まる。これが、日本的戦略の思考様式です。
将棋の駒はなぜ復活するのか|途中を失敗にしない世界設計
ここまで見てきた三つの事例は、すべて歴史の中の出来事でした。しかし、この思考は過去の戦場だけに存在したものではありません。最も完成度の高い形で、日常の中に実装されています。
それが、将棋です。
将棋では、取られた駒は盤上から消えません。敵に奪われ、持ち駒として再び使われる。この仕組みは、単なるゲーム性の工夫ではなく、日本的戦略思想をそのままルール化したものと見ることができます。
将棋において、敗北は不可逆ではありません。途中で形勢を崩しても、駒は資源として残り、配置を変え、役割を変えて再登場する。つまり、途中が失敗として確定しない世界が前提になっています。

これは、藤堂高虎の城と同じです。虎口で詰まる途中、設楽原で分断される途中、訥庵の政策で増殖が止まる途中。いずれも「最後で倒す」設計ではなく、途中で形を変えさせる設計でした。
将棋の駒が復活するのは、敵を完全に排除しないからです。排除しない代わりに、条件と配置を変える。すると、敵は敵であり続ける意味を失い、構造の内側に組み込まれていきます。
このとき起きているのは、勝敗の逆転ではありません。対立の枠組みそのものが溶けていく過程です。将棋は、勝つか負けるかを競うゲームに見えて、実は「勝負が固定されない世界」の設計図になっています。
だから将棋では、無理な攻めは損になります。倒しても終わらない。奪っても返ってくる。勝負を急ぐほど、途中で形勢を崩しやすくなる。結果として、争わない手、整える手、待つ手が重みを持ちます。
将棋の駒が復活する理由は、ここにあります。それは「優しさ」でも「情緒」でもなく、長期で構造を拡張させるための合理的設計なのです。
したがって、この三者をまとめるなら、和製戦略とは、勝つ技術ではなく、勝負が起きない条件を設計する思想である。
まとめ|戦略は理論ではなく「場」に刻まれる
藤堂高虎、設楽原の戦い、陶山訥庵。三者に共通していたのは、
相手を強くしない
数を力に変えさせない
流れをこちら側で決める
という発想でした。
戦略とは、戦場で頑張ることではありません。戦わせない構造を、先に作ることです。
そしてこの発想の核心は、「勝つ」ではなく「拡がる」にあります。無駄な争いを避け、相手を排除しない。すると、敵は敵であり続ける意味を失い、条件次第で味方に転じ、構造の内側へ組み込まれていく。
将棋の駒が復活するのも同じです。取って終わらない世界では、短期決戦は割に合わない。途中で形が変わり、役割が変わり、配置が組み替わる。その結果として残るのは、勝敗の誇示ではなく、壊れない構造の拡張です。
この視点を持つだけで、歴史も、仕事も、選択も、少し違って見えてくるはずです。


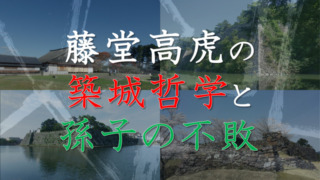



コメント